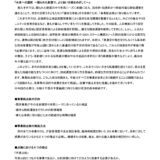7月29日(火)瀬戸市・尾張旭市・長久手市の3市議会による議員研修会に参加しました。
![]() 会場:尾張旭市文化会館
会場:尾張旭市文化会館
![]() 講演テーマ「令和6年能登半島地震〜地震と水害とこれからと〜」
講演テーマ「令和6年能登半島地震〜地震と水害とこれからと〜」
講師:槌谷雅也 氏
![]() 地震発生は令和6年1月1日 16時10分
地震発生は令和6年1月1日 16時10分
体感的には「2分ほど揺れていた」とのこと。
「止まらないんじゃないかと思うほど、長く揺れた」
「自分の命を守るのが精一杯だった」
地震、水害を経て、「人を助けるにはどんなスキルや装備が必要か」「誰も助けに来れないときでも」地域の防災力のために土屋氏は自らも被災しながら、避難所運営や地域支援に奔走された方です。支援の現場での体験を通じ、私たちが備えるべき“災害の本質”について、今できることを積み重ねる必要性を語ってくださいました。
とくに印象的だったのは、「新築より仮設で死んだ方がまし」と話す高齢者の声。被災前は観光地として賑わっていた輪島市も、いまは人口流出が進み、再建の見通しが立たない家庭が少なくありません。広大な土地を持つ高齢世帯にとって、2億円規模の住宅再建は現実的でなく、先行きへの不安が大きくのしかかっています。
また、輪島のような山間・港町では、災害規模があまりに大きく、「自衛隊も消防も来ない」と覚悟した方がよい、と土屋氏は言います。交通遮断や通信不通のなか、頼れるのは地域住民どうしの助け合い。通信途絶により、情報伝達は「紙と手書き」。唯一つながった携帯が情報収集の命綱になったり、工具の使い方一つが命を救う場面もあると強調されました。
講演では、社協・行政・NPOの連携のあり方、被災者支援の“顔が見える関係性”の重要性も語られました。復興は、物の再建だけでなく「人と人のつながり」の再構築。地域で防災を学び合い、日ごろから助け合う関係性を築いておくことが、最大の備えだと再認識しました。
能登の経験は、私たちのまちでも起こり得る現実です。忘れられていく被災地の声に耳を傾け、地域に根ざした支援の形を議会としても考え続けていきたいと思います。
カテゴリー